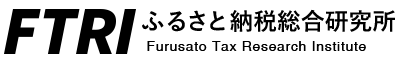【URL】
https://www.fnn.jp/articles/-/961798
【要約】
(1)長野県南箕輪村へ15,000円の寄付を行った寄付者に対し、梨の返礼品が届かず、村から返金案内が送られた。当初は「寄付金全額返金」案も示されたが、後に「返礼品相当額3,800円+迷惑料2,000円=5,800円返金」「翌年以降の梨送付」「寄付キャンセル」の3択に変更された。
(2)顧問弁護士の意見では、寄付金全額の返金は「違法な公金支出」に該当する可能性があり、自治体は「梨の時価相当額のみを返す義務がある」と整理。
(3)総務省は、返礼品が提供できなかった場合の返金ルールは統一されておらず、自治体判断に委ねられていると説明している。
(4)返礼品が送付できなかった理由は、登録した産地と実際の生産地が一致しなかったためで、地場産品基準に抵触する可能性を考慮し、村が送付を中止した。寄付者は約3,000人に及び、多数の問い合わせが発生した。
【コメント】
(1)返礼品の代わりに現金を返金する行為は、地場産品基準違反として扱われる可能性が高く、自治体の指定取消リスクが極めて高い。とくに「返礼品の代替として金銭を提供する」形態は、返礼品規制の趣旨に明確に反し、総務省が最も厳しくチェックするポイントである。今回の事案は、返礼品提供が困難になった際に、自治体が講じるべき対応の難しさを示す典型例といえる。
(2)返金方針が途中で変更されている点は、寄付者との関係構築にマイナスとなり得る。寄付者側の期待値とのギャップが拡大し、クレーム増加を招いた可能性があるため、初動と説明の精度が重要である。
(3)総務省の整理では、返礼品は「寄付の対価」ではなく、あくまで“お礼”としての位置づけであるため、法令上、返礼品不着=寄付金全額返金ではない。ただし、一般寄付者には理解されにくく、今回のような混乱につながりやすい。
(4)産地の不一致を理由に送付を控えた村の判断自体は、地場産品基準に則った適切な対応と評価できる。他方で、結果として3,000人規模に影響が出たことは、調達管理や品質確認フローの脆弱さを示しており、改善の余地が大きい。
(5)自治体が今後備えるべき再発防止策は以下のとおり。
1 事業者登録時の産地・加工地の厳密な事前確認
2 供給量・収穫量の変動に対応できるバックアップ調達体制
3 返礼品提供が不能になった際の「返金・代替・説明」標準フロー策定
4 寄付者向けの丁寧な説明(特に返礼品は法的な“対価”ではない点)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ふるさと納税制度に関する情報共有にご協力いただけますと幸いです。
近年、ふるさと納税制度における法令違反が相次いでおり、自治体が指定取消となる事例が増加しています。
私たちは、こうした事態を未然に把握し、自治体が指定取消に至るリスクを低減したいと考えております。
以下のフォームにて、無記名で情報をご提供いただけます。
https://forms.gle/sMFG6kd5vbff8zuZ7
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
株式会社ふるさと納税総合研究所
当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務
を通じてふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。
業務や取材をご依頼の方はお問い合わせフォームからお願いいたします。
https://fstx-ri.co.jp/contact
代表取締役社長 西田 匡志 (中小企業診断士)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー